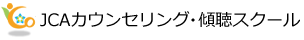前回チャンクというお話をしました。
チャンクとは、人が情報や状況を一つのかたまりとして捉える傾向があり、
この情報のひとかたまりのことをチャンクといいました。
(詳しくは前回の記事をご覧ください。)
さて、このチャンクですが、人によって、
物事を抽象的に捉えやすい人(チャンクアップ傾向のある人)
物事を具体的に捉えやすい人(チャンクダウン傾向のある人)
がいます。
相手がどんな傾向がある人かによって、
コミュニケーションをとるときに役に立つ為、
ちょっと簡単に、それぞれをご説明しますね。
そもそも、チャンクアップ・ダウン傾向がある人は、どんな人たちなんでしょう?
チャンクアップ・チャンクダウン傾向がある人はどんな人?
同じような出来事が起きた時の対処で説明していきますね。
A:ある概念を学んだ時に。
B:仕事でアドバイスを求められた時に。
B:仕事で部下が失敗したけど、うまくいった場面で。
物事をざっくり捉える傾向がある人がチャンクアップ傾向がある人
例えば、
A:結局それって○○ってことでしょ?
B:とにかく仕事っていうのは、うまくやればいいんだよ。
C:確かに失敗したけど、そんな細かいこと気にするなよ、お客さん喜んでいたんだからそれでいいよ!
といった感じです。
チャンクアップ傾向がある人は、森を見て、木を見ず。(チャンクアップ傾向)
・大雑把な性格とよく言われる。細かい事は気にしない。
・物事のポイントを抽出して、そのポイントを捉えるのが上手い方です。
・物事の全体像をとらえるのが得意だが、細かいところには目がいかない。
・物事をざっくりと捉えるために、細かい点を把握するのが苦手。
・その為、人の気持ちに対しても大雑把に分けて捉える傾向が少しある。
それが弊害となり、人の細かい気持ちを見逃すこともある。
物事をより詳しく捉える傾向がある人がチャンクダウン傾向がある人です。
例えば、
A:それって○○何だと思いますが、ちょっとそれってよ~く見ていくと△△との違いがありますよね。
B:仕事っていうのは、Aという要素と、Bという要素があって始めてうまくいくから、うまくやっていくにも、一つ一つのプロセスが大事なんだ。
C:あの時に○○と言葉をではなく、△△って声を掛ければよかったね。ただ結果的にあの瞬間に、気持を切り替えて真剣に目を見て真摯に××な対応ができたのがよかった。
チャンクダウン傾向がある人は、木を見て、森を見ず。(チャンクダウン傾向)
・細かい性格とよく言われる。細かい違いに気づける。
・物事の詳細を捉えるのが得意。
・その分、物事の全体像を捉えるのが苦手。
・詳細にものごとを区別できるため、ミスが少ないが、気にしすぎるところも。
・人の細かい気持ちを見逃すこともある。
・自らの体験も詳細に思い出したりするために、
プラスの体験など気持ちを感じやすい、その分マイナスの体験も詳細に思い出し、
嫌な気分を強く感じてしまうこともある。
・その分、物事の全体像を捉えるのが苦手。
このように、チャンクダウン傾向のある人、チャンクアップ傾向がある人は、
それぞれ一長一短ではありますが、それぞれの特性があります。
コミュニケーションを取るときに、この特性を理解しておくのが役立つことがあります。
人は、自分が普段しないことすると成長の幅が広がる。
僕たちは、ついつい自分の得意なコミュニケーション(普段から用いている)を取りがちです。
あんまり苦手なことってしないですよね。
物事を詳細に捉える傾向がある人は、
ざっくり物事を捉えるのが苦手。
物事を抽象的に捉える傾向がある人は、
詳しく物事を捉えるのが苦手。
だから、ついつい自分の得意なことばかりをやりがちです。
でも、それだけばかりを繰り返していたら、学びや気づきはなかなか生まれません。
普段自分がやらない対極のことをする。
この時に人は多くを学び、気づくことがあります。
コミュニケーションの場面でも同じです。
ついつい、詳細に捉える傾向がある人には、
チャンクアップしてもらう。
つまり物事を抽象的に捉えてもらう。
「そういう細かいところまで見ていてくれてありがとう。それで全体的にどんな印象かシンプルに教えてくれる?」というように。
ついつい、ざっくり捉える傾向がある人には、
チャンクダウンしてもらう。
つまり細かい所にも目を向けてもらう。
「ポイントはわかったんだけど、もうちょっと詳しく教えてくれますか?」というように。
すると、その人のコミュニケーションの幅が広がっていきます。
人は対極を体験することにより、普段意識しないことが見えてきます。
物事をざっくり捉えて、細かいことを見逃しがちな人は、
そういった今まで見逃しがちだった小さなことにも目が向けれるように。
物事を詳しくとらえすぎて、全体を見る事ができない人は、
物事の要素を捉えるトレーニングや、全体像を把握するトレーニングに。
相手がどんな傾向にあるのかを捉え、
その人の幅が広がるようにコミュニケーションを取っていくのも、
意味がある時間ではないかなって思います。
どうぞ試してみてくださいね。
言葉で書くと難しいですが、実際にやってみると案外簡単なものです。
実際に肌で学びたい方は、傾聴基礎コースへ。