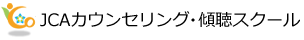セラピーや技術は、希望の伝達でなければならない。
誰の言葉かは忘れてしまいましたが、
僕はこの言葉が好きです。
自分が出来ているかどうかは、
思いっきり棚の上に上げておくとして(滝汗)、
この言葉が好きです。
セラピーというものは、
どちらかというと問題点を修正する方向性でデザインされていることが多いですが、
問題を直すという視点や、変えていくという視点は、
今の自分がダメだという前提があります。
勿論すべてのセラピーがそうであるわけではありません。
ただ、僕たちは相手に何かを働きかける時、
それがどのようなコミュニケーションだとしても、
どのような技術をその中で用いようとも、
どのような介入(セラピー)をしようとも、
それが相手にとって「希望」になるのか、
というのは、とてもとても大切です。
大切という言葉では語りつくせぬほどに。
自分が掛ける言葉が、
相手にとって希望になるのだろうか?
この質問の技術や、
このコミュニケーションの技術は、
「相手」にとっての希望となるだろうか?
僕たちがこれから働きかけようとしていることが、
「希望の伝達」になるだろうか?
勿論、希望が生まれるかどうかは、
僕たちの関わり方ですべて決まるわけではありません。
でも、僕たちは、
自分たちが用いる働きかけに、
希望をのせて、
願いをのせて用いることが大切なのではと思うのです。
僕たちがこれまで学んできたことは、
僕たちがこれからも学んでいく必要があることは、
相手を変える技術ではなく、
相手の中に光を見る目であり、
それを感じる体を持つことであり、
痛みの奥にある希望の声を聴く耳を持つことなのではと、
きれいごとかもしれないけれど思うのです。
セラピーや理論を、
”変化の技術”としてみるのではなく、
”変化の為の理論”として学ぶのでもなく、
それがどう相手の希望に繋がるのか?
それを身に付けることによって、
自分は相手のどんな希望を見ることが出来るのか?
そんな視点がきっと大切なのではないかと、
最近思うのです。
こうやって人は変わるという理論よりも、
こうやって人は変わることがある。
だからこういった視点を持つことも大切だ。
何故ならそういう視点を持てば、
相手の中にまだ希望があると見出せるから。
相手の希望が失われていたとしても、
援助者がそれを見い出すことが出来れば、
その光は再び輝きを増すのだと、
そんなことを思うです。
そして少なくとも僕は、
変化の技術や理論よりも、
これからは、そんな視点を学び、
そんな目で理論を学んでいきたい。
繰り返しにりますが、
こういったことが出来ているわけではないので、
思いっきり自分のことを棚に上げています…
よ。
終わり。