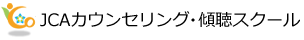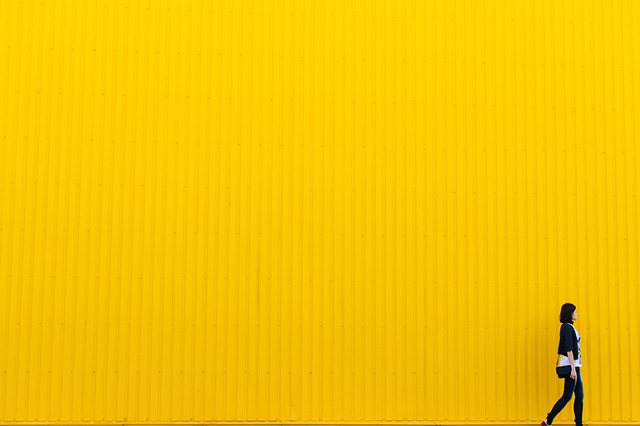「人はみんな違う。」
これは、当然のことではありますが、
どのようにその違いを捉えていくのかを教えてくれるところは、
実はあまりありません。
心理学の理論を教えてくれるところはありますが、
理論も一般的にこういった傾向があるということですし、
タイプわけになりますから、
その中間の人や個別性を捉えることはなかなか難しいのです。
例えば、うつ病を例に挙げると、
うつ病は大きく分けて気分の浮き沈みがある双極性障害と、
気分が上がらずに沈んだままの大うつ病性障害の二つに分けられます。
そして症状によってそれぞれさらに小さな分類がうつ病にはありますが、うつ病という大きなカテゴリーにおいて、食欲・性欲減退や増加、朝気分が沈む、希死念慮などの共通点があります。
一方で、気分の浮き沈みがあることやその期間の長さ等のその他の要因で相違点もあります。
このように共通点と類似点がうつ病にはあるわけです。
そして、心理学の理論にも同様に共通点と類似点がありますが、
そこを自分なりに捉えていくと、その人の個別性が見えてきます。
例えば、うつ病でいうと何をキッカケにうつ病になったのかによって、
対応も変わってきます。
・大切な人に喪失
・仕事による過重なストレス
・燃え尽き
・一気にストレスがかかってしまったのか、それとも蓄積なのかetc.
といった要因は、相違点の要因となりますから、
そこにその人独自の個別性があり、
そういった個別性を捉えていくと、
いわゆるうつ病の人に対しては、
認知行動療法をというような単一な選択ではなく、
個別性を重視した手段を選べるのです。
また、個別性を捉えるといった場合、
こういったライフイベントの観点やその他にも例えば、
・感情+感情の対象
(ex.怒りであれば”誰に”怒りを向けているのか。悲しみであれば”何”を失ったと感じているのか。)
・状況要因
・環境要因
・キッカケ
・気持ちの表現の仕方
・意識の向け方(内向・外向)
・いつ・どこで・場所は・誰に対して?
といったような相違点を捉えられるようになってくると、
うつ病であるが自責傾向は少ない。
うつ病であるが特定の状況の時だけ特に酷くなる(良くなる)。
といったようなことが見えてくるようになります。
共通するところと相違点を自分なりに理解する。
そんな取り組みがとても大切であり、
僕自身も今こういったことを自分の観点から理解できるように励んでいます!