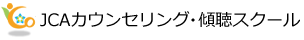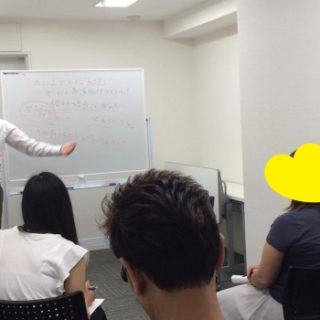「話をただ うんって聴くのが傾聴と思っていた。」
今日の講義を受けていた受講生からこのような感想が出てきました。
確かに傾聴というと、ただ聴いているイメージがありますよね。
でも実は聴くだけではありません。
聴いたことに対してフィードバックをしていったり、
相手の思いをくみ取って言葉にしたり、
相手の非言語に気づいて言葉にしたり、
色々とやることがあるのです。
今日の傾聴基礎コースでは、そのいろいろとあるうちの
相手の気持ちを汲み取り言葉を掛けるねぎらいの講義を行いました。
ねぎらいは、相手の気持ちを汲み取り言葉にしていくことですが、
汲み取っていくには、相手が感じていることに思いを馳せていくことが大切です。
それは例えば、次のように…。
・相手は今どのような気持ちなのだろう?
・相手は本当はどうしたかったのだろう?
・どういう人生を歩んできたらこのような言葉が出るのだろう?
・相手は今どのような気持ちを抱えているのだろう?
・相手が期待していたことは何だろう?
・それは叶ったんだろうか?叶わなかったんだろうか?
などなどこういった事に思いを馳せて、
相手の気持ちを受け止めて、
その歩んできた道のり、相手の人生や相手そのものに対して
労をいたわる言葉がけがねぎらいです。
(ねぎらいは褒めると違いますが、その違いは詳しくはこの記事をお読みくださいね。)
今日の基礎コースでは、そのねぎらいのトレーニングを行いました。
最初は褒めてしまったり、ねぎらいと褒めるの違いに頭を抱えていらっしゃる方や、
いやぁ~難しいと感じる方も多かったですが、皆さん一生懸命に取り組まれていました。
技術としてねぎらおうとすると、ねぎらえなくなるのも当然です。
それはねぎらいは、技術の部分も勿論ありますが、
相手に思いを馳せれば自然と湧き上がってくる言葉でもあるからです。
とはいえ、最初はそうもいかないところがありますから、
まずは相手に思いを馳せる想像力を磨いたり、
相手に気づける量を増やしたりすることが大切です。
そうしていくと、相手の様々な気持ちや思いに対して
少しずつ気づける量が増えてきます。
気づける量が増えてくると、自然と相手に対して思いやりが湧いてきます。
するとねぎらいの言葉も浮かびやすくなってくるのです。
言葉で書くと簡単ですが、その道は一朝一夕では必ずしもありません。
地道にトレーニングを重ねて、着実に力をつけていくことが大切です。
地道ではありますが、聴く力は誰でも伸ばす事が出来ますし、
ねぎらいの言葉も、その言葉がけも自分なりに懸命に取り組めば身についてくるものです。
そう、学ぶことをやめずに続けていけば、着実に身になるものなのです。
もちろんその学ぶ中で、それこそ自分をねぎらいながら取り組んでいけると理想ですね。
地道だけれど、着実に身に聴く力を身につけたい方は、
是非 傾聴基礎コースにお越しくださいね。