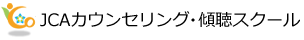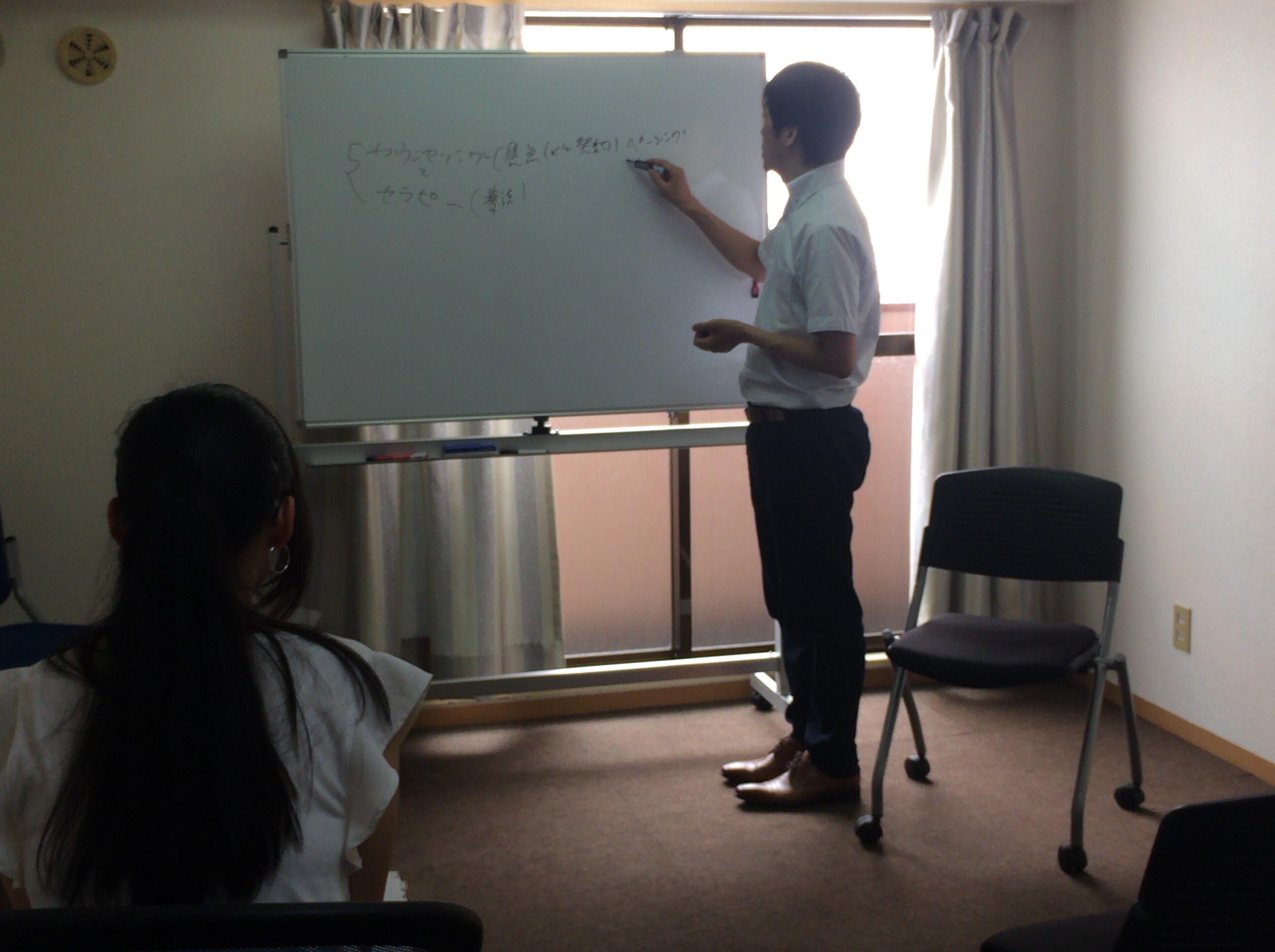「自分なりに練習することも大切ですが、第3者からフィードバックが一番大切です。」
どうやったら傾聴が上手くなりますか?
という受講生の質問に対して僕はこのように答えました。
自分なりに出来ることは沢山あります。
自分の状態を整える。
外に繰り出して、カフェで人のお話にそっと耳を傾けて、
その人の独特の話すリズムや、声のトーンなどに耳を澄ませてみる。
待ちゆく人を観察してみる。
ゆっくりと深呼吸をして、自分を感じてみる。
今どんな気持ちだろう?
今何を大切にしたいだろう?
今どんな気持ち?
本当はどうしたい?
そうやって自分を感じてみる。
自分に気づくことは、相手に気づくこと。
だから自分を感じることはとっても大切。
ネットで悩み相談を閲覧してみる。
自分ならどう答えるか考えてみる。
どんな気持ちがあるんだろう?
そんな妄想をしてみる。
どんな気持ちで書いたのだろう?
思いを馳せてみる。
そう、一人で出来ることは沢山あるのです。
でも、一人だとできないことがある。
それは、自分の癖を知ることであり、
別の視点での関わり方を学ぶことや、
先人に知恵やアドバイスを直接頂くことです。
一生懸命に自分でやってもやっぱり壁にはいつかぶつかってしまいます。
ですから、当スクールではもしあなたが壁にぶつかった時に、
その壁を突破できるように、徹底的に実践練習する講座をしております。
実践練習の内容。
「Active listening practitonerコース」では、傾聴の実践練習を徹底的に行っています。
基礎コースで身に着けた内容が現実の場面で出来るように、
様々な練習をしています。
例えば、受容と共感の練習をしたり、
質問とケアをセットで行えるように練習をしたりします。
「今の言葉は、相手の葛藤の一方の気持ちを受容は出来ていますが、もう一方の側が受容できていなかったので、「でも…。」という言葉が出てきてしまっていました。どう受容すればよかったでしょうか?」
「今のは、気持ちを受け止めているようで相手からしたら否定されているように感じたかもしれません。どの部分がその可能性があったでしょうか?」
「質問のタイミングや内容は、とても的確ですので今度は質問に対して答えてくれた時に、それに対して感謝でもいいですし、ねぎららいでも受容でも構いませんので、コメントするようにしてみましょう。」
このように、受講生同士で練習をしてもらいながら、
実践的に聞けるように講師側がフィードバックをしていきます。
また、どこが出来ていなかったのか、
どこかが出来ていたのかを客観的に見ないとわからない時がありますので、
希望の方にはビデオをとりながらフィードバックを行っています。
希望しない場合は、あるタイミングで敢えて会話を中断し、
今の場面はどう改善したらいいでしょうか?
とリアルタイムで今起きていることをご本人が理解できるように、
その場で修正ができるように援助をしていくこともあります。
こういったプロセスの中で、自分の聞くスタイルを振り返りながら、
自分の聞き方を磨いていってもらいます。
頭で考えても体がついてこないことは沢山ありますから、
少しでも多く練習を重ねてもらい、日常で出来るようにお力添えをしています。
傾聴は、スポーツの練習ようなところがありますから、
何度も反復して練習していくことで聞き方が身についてくるのです。
勿論、受容や共感以外のトレーニングも行っています。
・ねぎらいのトレーニング
・質問とケアのトレーニング
・非言語コミュニケーションのトレーニング
・意図を持って聞くトレーニング
・実際にミニカウンセリングをするトレーニング
などなど沢山のトレーニングをしています。
聞くというコミュニケーションは、実践を通して身につけていくしかありません。
ただ、現実生活で失敗できないこともあります。
上手く聞けなかった経験も大切ですが、人を傷つけてしまうこともあります。
だから安全な場で挑戦して失敗してみる。
試行錯誤してみる。
そんなこともとっても大切なのです。
傾聴実践講座「Active listening practitonerコース」は、こちら!
聞く練習を積みたい方は、是非お越しくださいね。