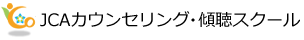外在化とは、心の問題を外側から捉えられるように(客観視)することで、
問題への対処可能性を上げたり、自分の外側にあるものとして対処することで、
解決しようとする取り組みのことです。
この技法は、よくナラティブセラピーといわれる心理療法で用いられる技法ですが、
勿論家族療法や、その他のカウンセリングにおいても用いられています。
カウンセリングで使われているというと、
少し特殊な印象を持つかもしれませんが、実は僕たちは自然とやっていたり、
やられていたりすることがあります。
例えば、次のように問題に名前を付けたりすることも外在化です。
子供「お腹いたいの…。」
母「チクチクさんがいるのね。」
子供「そう、チクチクさんがいるの。」
母「チクチクさんは、ずっとそこにいるの?」
子供「ううん、さっきから来たの。」
母「じゃ~チクチクさんが、またどこか行くまで待っていようね。」
といように、お腹の痛みをチクチクさんとして擬人化したわけです。
このように擬人化することで、お腹の痛みはチクチクさんが悪いのであって、
本人が悪いのではないという事となるわけです。
この他にも例えば、「お酒がのもうって誘ってくるから悪いんだよ。」とか、
「自分の中にいるなまけ虫が悪いんだよ。」といったように、
問題を本人に帰属するのではなく、自分のわきへ置き、
そのわきへ置いた自分から切り離された対象が問題であるとする捉え方は、
外在化の手法でよく行われる手続きです。
人間が悪いのではなく、問題が悪いのだ。
このように外在化は考えるのです。
そして、問題を自分の外側へと客観視することによって、
自分から切り離して心理的な問題へと対処するのです。
人は、自分の心の問題に対して圧倒されてしまうときもありますし、
過度に自分を責めてしまったり、傷つけてしまう時があります。
そんな時、僕たちは自分ではそういった心の問題を手に負えないと感じて、
その問題に圧倒されてしまうことがありますから、
外在化をすることで、その人自身からその問題を切り離す援助ができるのです。
実際に用いた例ですと、
「過度に自分を責めたり、落ち込むのは、あなたが悪いのでありません。」
「うつ病という病のせいであって、あなたが悪いのではないのです。」
「ずいぶんうつ病というやつに苦しめられてこられましたね。」
といったように、うつ病をその人そのものから切り離してカウンセリングをしたことがあります。
勿論外在化は、外在化した後の展開が何より大切ですが、
切り離すことで自分のせいではなくて、その外在化した対象が問題となる為、
少し楽になったり、必要以上に自分を責めてたり、苦しんだりしなくなることがあるのです。
また、外在化により自分全部が悲しいんじゃなくて、苦しいんじゃなくて、
自分を悲しませる悲しみが、悲しんでいる。
自分を苦しませる苦しみが苦しんでいる。
というその自分の一部分がそうなのであって自分そのものではない
という認識も芽生えるため、
問題がそれだけで小さくなることも起こりえるのです。
僕たちは必要以上に悲しんだり苦しむ必要はありませんから、
そんな援助の仕方も大切なのです。
他にも、自分の胸の痛みや苦しみに、
イメージ療法のように形や色などや重さなどの視覚や体感覚情報を付加することで、
外在化するという手法もあります。
また、「ついつい不安になっちゃうんだ。」という方に対して、
「不安にさせちゃうやつがいるんだね。」というのも外在化です。
心の問題を絵に描いてみるというのも外在化ですね。
外在化は、このように問題を自分の外側へと置くことによって、
自分から切り離して心理的な問題へと対処する取り組みなのです。
外在化に関しては、ナラティブセラピーの本などにも詳しく書いていますので、
ご興味がある方はご覧くださいね。