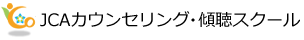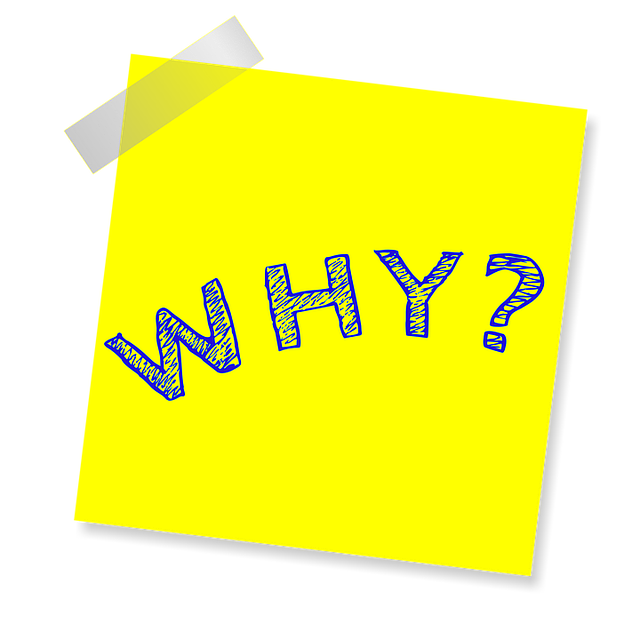非言語の観察力を鍛える時は、
大きく分けて二つの方向性があります。
1つ目は、直感で浮かんできた印象の根拠を探る。
2つ目は、見て取れた素材から概念を構成する。
というやり方です。
これは、ある本を読んでいた時に、
アートの見方もそうなのだということが書いてあって、
ビックリしました。
さてさて、
ちょっと具体的に上げた2つのやり方が抽象的なので、
具体的に説明しましょう。
1つ目のやり方とは、僕たちが普段直感的に相手に対してやっているやり方です。
「第一印象」という言葉があるように、
僕たちは意外と(?)、相手をすぐにこんな人と判断します。
経験を通して直感的に相手への印象が湧いてくるのです。
そして、これが相手を観察している時にも出てきます。
「なんか大雑把そう。」
「優しそう。」
「厳しそう。」
といったようにです。
でも、大抵こういう印象というのは、
何となくで大雑把に捉えていることが多いですから、
その大雑把さを取り払い、
判断材料=根拠を明確にしていくのです。
ですから、
「なんか優しそう。」
と観察して感じたのだしたら、
「どこからそう思ったんだろう?」
とその根拠を振り返って探っていきます。
これをやっていくと、
自分がどこを見て優しいと判断しているのかが見えてきますし、
細かく見ていくと、
この目は優しいというよりも、
愛情深い目だなとか、
そういった微妙な違いが見えてきますし、
何より何となくの印象で相手を捉えなくなります。
ここがとても大切です。
さて、二つ目の方法は、
観察できるところをすべてノートにメモして、
そこからどのような人なのか、
どのような気持ちなのかを想像するというやり方です。
見て取れたところをすべて列挙して、
そこからパズルのピースを集めて、
1つの絵を作るように相手の気持ち/人柄などを想像していきます。
例えば、
話す時に姿勢が前のめりになり、
よく何かを思い出したかのように上を見て、
口角を上げてほほを緩める。
話す速度は早く、
どちらかというと高めの声であるが、
声に重さがある。
途中で言葉を噛んだり、
表情がこわばったりはしていなく、
表情は終始口角が上がり、
目も柔らかい印象である。
人の目を見て話す時間がながく、
あまり周りの人に目が行かない。
こういった要素から、
人が前のめりになる時というのは、
気持ちを伝えたい時とか、
重要な話をする時、
焦っている時であることが多い。
話すのが早いということは、
焦っている時にも早く話したい時にも、
気持ちを伝えたい時にも該当するが、
焦っていれば、
表情がこわばっていたり柔らかい印象はないはずだし、
重要な話であれば話す速度はゆっくりなはずだ。
ということは、気持ちがを伝えたいのだろう。
そして、表情と声色とよく上を見て話し、
その際にほほが緩む感じは、
きっと楽しかったり嬉しかった体験を話しているのであろう。
といったように、素材を組み合わせて気持ちなり、
その人となりを推理していきます。
何度か紹介しているやり方ですが、
着実に実力は身につきますからやってみてくださいね。
コツは、
直感的に印象が沸き上がったら、
「どこからそう思ったんだろう?」と自問すること。
直感が沸き上がらなければ、
見て取れること、
聞いて取れることをすべてメモして、
「これこれこういうしぐさや表情をしているということは、
どんな気持ちだろう?どんな人だろう?どういうことを表現しているだろう?」
と推理してみることです。