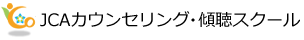カウンセリングの仕事をしていると、
多くの心理的苦しみを抱えている方と出会います。
うつ病の方、パニック障害の方、不安症の方、
離婚の危機にある方、ギャンブル依存の方、
恋愛に悩む方など、その内容は本当に様々ですが、
”苦しみを抱えている”ことは共通しています。
カウンセリングでは、その苦しみを受け止め、寄り添い、
何がそのような苦しみを生んでいるのかを共に理解しようとします。
僕自身もカウンセリングをする時は、
「どのように苦しいのだろう?」
「何が苦しみを生み出しているのだろう?」
ということを理解し、
思いやりを持ちながら接するようにしていますが、
先日までこの”苦しみ”には、大きく分けて二つあることに気づきませんでした。
心理的苦しみは、
「降りかかってくる苦しみ」
と
「自らが生み出している苦しみ」
の二つに大きく分けられるのです。
「降りかかってくる苦しみ」というのは、
環境要因です。
ご本人がその苦しみを生み出しているのではなく、
職場環境やそこでの人間関係、家庭環境・災害などの外的要因が
ご本人に降りかかってくる場合がこれにあたります。
例えば、パワハラ・いじめ・災害・モラハラなどです。
「自らが生み出している苦しみ」は、
自らの心の癖が関係しています。
例えば、理解して欲しいのにその気持ちが怒りとして出てしまって、
相手を結局遠ざけてしまい、それがますます分って欲しい気持ちに火をつけ、
相手をさらに遠ざけてしまい、孤独感や寂しさ・悲しに繋がってしまう…
といったように個人の心の癖が関わってくる部分です。
僕自身、この苦しみの質を分けられていなかったので、
多くの心理的苦しみをご本人に起因するものとして、
認識したり対処しようとする傾向がありました。
でも降りかかってくるものは、
ご本人には変えられませんし、
それをもしご本人が自分のせいだと感じていたとしたら、
そんなことはないと保証をしたり、
環境要因として対処を考えることが大切ですよね。
一方で、「自らが生み出している苦しみ」であれば、
個人の内界で起きているものとして、
サイコセラピーやカウンセリングなどで対応が出来ます。
このように目の前の方が抱えている苦しみの質を
分けて捉えることが出来るようになると、
対処の仕方が変わってくるのです。
何が苦しいのか?を理解することも大切ですが、
同時に「その苦しみは、降りかかってくるものなのか?それとも心の癖として出ているものなのか?」を理解することも大切なのです。