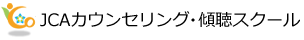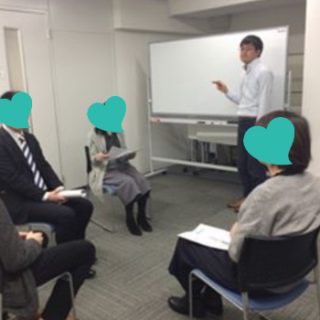ども!講師の野川です。
昨日は横浜傾聴基礎コース4期の第3回目。
早いもので、昨日がもう終わってしまったので、
4期もあと1回となりました!
いやはや早いですね。
昨日は傾聴というよりもちょっとカウンセリング色が強く、
質問も、実際に福祉系や対人援助職の方が多かったからか、
結構突っ込んだ内容となりました。
「問題の焦点化って難しいですよね。どこまで絞ればいいのか…。」
といった質問や、
「問題の焦点を絞っていっても、あんまり掘り下げすぎてもダメだし、
こちらこれだよって言ってもダメだし…。」
といったようなお話も出たので、
ちょっとだけ傾聴とは違いますが焦点化のお話もさせてもらいました。
相手が扱いたいテーマを絞ること=問題の焦点化
勝手にあなたが分かっている風でお話を進めてしまいました。(^^;
失礼しました!
”問題の焦点化”という言葉ってあなたは聴いたことありますか?
すごく簡単に言うと、相手が扱いたいテーマ(問題)を一つに絞ることです。
僕たちって悩むと、結構いろんな問題が出てくるのです。
「母親との関係を改善したい。」
といった時に、詳しく聴いていくと、
「母親に対してついつい怒りっぽくなってしまう自分がいて嫌だ。」
「母に対して実は罪悪感があって、過去にこんなことがあって…。」
「でも、やっぱりけっこう厳しく育てられて、ひどいことを言われたから許せない気持ちもあって…。」
といったように、いろんなテーマが出てくることって多いのです。
でも、カウンセリングの場面ではテーマは基本的には、
一つしか扱えませんから、テーマを絞っていく必要があるのです。
今あげた例だと、3つテーマがでてきていますから、
3つのうちからどれを”本人”が扱いたいかを決めてもらうプロセスを、
焦点化と言います。
焦点化は基本的には相手がやることです。
この問題の焦点化は、カウンセラー、つまり援助側ではなく、
相談者本人がやります。
それは、取り組む問題を決めるのは本人だからです。
話を聞いてると、問題はそこではなくて、本当はこっちの方がいいんじゃないかなって、
そう思うことがありますが、それは余計なおせっかいなのです。(^^;
なので、それが問題じゃなくてあなたの問題はこっちですよ。
って言った時って大体うまくいきません。
なぜかというと、本人が決めたテーマ(問題)ではないから、
取り組む意志が減りますし、逃げ道ができます。
「あの人がこういったから…。」って。
そして、そもそも、その問題に取り組むのは援助者じゃありませんから、
こっちからあなたの問題はこうですよって言った時に、
責任がとれませんし、余計な問題が増えてしまう危険性すらありますから、
基本的にはこちらから指摘はしないのです。
基本的にはと書いたのは、
例えば相談者がこの問題を扱いたいと言ってきた時に、
わざとこちらの方が問題ですよ。
ってテーマを変えて提案することがあります。
それは、結構な熟練と見立て(治療方針)があって、
”こっちの方が問題”といった問題に取り組んでもらうことで、
相談者がいう問題も解決するというプランがある場合です。
ただこれはとっても難しいので、よっぽどの自信がない限り、
やらない方が無難です。(^^;
なので、基本的には、本人が”これが問題だ”という問題を扱うことになります。
問題の焦点化の過程では、ねぎらいを。
問題を絞っていく過程では、
詳しく一つの問題(テーマ)について聞いてくことになるので、
相手に負担をかけるのです。
嫌な気持ちの時の体験を思い出してもらったりすることもあったりするので、
再体験する可能性がありますし、
質問に答えていくこと自体、自分の気持ちを感じていくこと自体が負担になりますから、
ねぎらっていくことが大切になります。
つまり、問題の焦点化では心のケアも同時に行っていくことが大切になるのです。
「よく勇気をもって答えて頂きました。」
「大きなテーマを向きあって言葉にしてくれてありがとうございました。」
「話を聞いていて、胸が締め付けられる思いでした。
きっと、当時のあなたはもっとずっと苦しかったのですね。
よくこれまで耐えてこられましたね。」
といったように、ねぎらうことで心のケアを行っていくことが大切なのです。
そしてねぎらっていくことで、テーマ(問題)へ取り組む意志も強まりるのです。
焦点化では、非言語のフィードバックも大切。
問題の焦点化の過程では、ねぎらいと同時に非言語のフィードバックも行っていきます。
非言語のフィードバックとは、例えばこんなことです。
「なんだか自信がないように聞こえます。」
「目に力が入ったように見えます。」
「話を聞いていて、なんだか胸のあたりが苦しい感じがします。」
といったように、
相手の表情やしぐさ、姿勢など”目”から見た非言語をフィードバックしたり、
相手の声のトーンやテンポ・リズムの変化など”耳”から聞こえた非言語をフィードックしたり、
相手から伝わってきた”体”感覚をフィードバックするといったように、
相手の声なき声をフィードバックすることを非言語のフィードバックといいます。
人の気持ちって言語、つまり言葉の内容だけに表れているわけではありません。
話し方や、姿勢、表情、声のトーン、伝わってくる感じなどの非言語にも如実にあらわれますから、
そこをフィードバックすることってとっても大切なのです。
なぜかというと、人が問題を抱える時は、気持の整理が出来なくて困っていることが多い為、
その気持の部分をフィードバックすることによって、相手は…、
・自分の気持ちに気づいたり、吟味するキッカケになったり、
・気持ちが整理されたり
する為、非言語のフィードバックってとっても大切になるのです。
どこまで問題を絞ればいいのか。
こんな過程を通して、問題の焦点を絞っていくわけですが、
冒頭の受講生の質問にあった「どこまで問題を絞っていけばいいのか。」
というところですが、どこまで焦点を絞るかは、本人次第なのです。
なぜな~ら、テーマは本人が決めるからです。
そして、この「どこまで絞っていけばいいか」っていう言葉は、
「こちら側」が頑張らなきゃっていうニュアンスもありますから、
こっちが頑張ってしまうと、相手が頑張ってくれず…。
なんてことにもなりますから、うまくいかないこともあるのです。
ただ、そうはいってもね~!って声が聞こえてきそうなので、(汗
焦点化で大切なことをもう一つだけお伝えしますね。
それは「確認」をすることです。
「あなたが取り組みたいのは○○でいいんですね?」
って、確認をすることです。
そこで、違うと言われば、違うテーマを扱えばいいですし、
そこでそうなの!って言われればそのテーマを扱えばいいのです。
焦点化をするのは、問題を絞った先に”サービス”を提供する為。
さて、そもそも問題の焦点を絞るのは、その先に”サービス”を提供するからです。
カウンセリングだったら乗り越えるための”取り組み”だったり、
営業だったら”商品・サービス”を提供する為だったり、
いずれもそのテーマを解決する為の”サービス”を提供する為です。
そのサービスを提供することで、幸せになってもらったり、
日常生活快適に過ごしてもらう為です。
ということは、焦点を絞るだけだと意味がないってことなのです。
なぜこんなことを敢えて書いているかというと、
世の中には結構この問題の焦点を絞って、
絞ったままにしておく方が少なくないからです。(^-^;
”あなたの問題はこうです。”
”いやいや、あなたの問題は○○じゃなくて、△△です!”
といったように、指摘するケースが多いようですが、
言われた本人がそれを信じちゃうと、
問題が増えてしまったり、
「結局問題はわかったけど、それで?」っていう事になってしまうのです。
それだと、結局傷口が開いたまま、閉じてない状態なので、痛いだけになってしまうのです。(^^;
その為、問題の焦点化を行う時は、
サービスの提供を行うという前提のもと行うことが大切なのです。
さてさて、ちょっとだけ長くなりましたが、
昨日の傾聴講座では、少しだけこんなお話もさせてもらいました。(^-^)
次回の傾聴基礎コースは2/4(土)スタートでございます~!
詳しくはこちら!