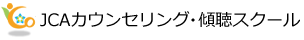以前こんなことを言っている方がいました。
「傾聴できてない人が多いんですよね。」
「だから基準を作った方が良いと思うんですよね。」
「この場面で、何回オウム返しが出来ていたかとか、頷けてなかったとか…。」
確かに、きちんと聴けているかどうかの基準って大切ですよね。
どこまで自分が聴けているのか、現在地を知らないと上達できないですからね。
ただ、これってちょっと難しいんです。
きちんと聴けているかの基準は、
何回頷けたという基準にあるわけでもなく、
何回オウム返しが出来たかにあるわけでもなく、
どれくらいの割合で相手が話していたかにあるわけもないからです。
きちんと聴けているかどうか判断するのは、
第3者ではなくて、実際に話を聴いてもらった人です。
だから、如何にオウム返しが出来ていようが、
頷けてようが、相手が良く話してくれていようが、
相手が「きちんと聴いてくれてないな…」って思ったら、
それは聴けていなんです。
だから、基準は技術や客観的に見てわかるものに表れにくく、
その判断基準を設けるのは難しいのです。
そんなことよりも、
「本当はこの場面でどう聞いて欲しかったですか?」
「どの点が聴いていないなって感じましたか?」
「本当に話したいことは話せましたか?」
と、相手からのフィードバックを基準とした方が、
もっと意味がある気がします。
いつだって、傾聴する時の主役は相手なんですから。